第40回 けいはんな「エジソンの会」
開催概要
モビリティ市場への新たな挑戦
| 講師 |
|
|---|---|
| 開催日時 | 2022年10月14日(金)14:00~17:30 |
| 開催場所 | 公益財団法人国際高等研究所 |
| 住所 | 〒619-0225 京都府木津川市木津川台9丁目3番地 |
| 概要 | 自動車業界は「100年に一度の大変革期」の中にあると言われていますが、社会的機能としての「モビリティ」の提供者となることで、その役割が大きく変わろうとしています。脱炭素が国際潮流となる中、ポリシーメーカー主導のEVシフトが加速し、完成車メーカーを頂点とした産業構造の変革と相まって、モビリティ市場はかつてないほどの激変期を迎えています。 第40回会合では、国内外の自動車産業に精通し、モビリティ業界で世界最大のブロックチェーン国際標準化コンソーシアムMOBI(モビ)でアジア人として唯一の理事を務める深尾三四郎氏より、Web3.0時代に入った世界自動車産業の最前線や欧米でのEVシフト政策の狙い、脱炭素社会実現に向けた国際的なルールメーキングの争いをご解説頂きます。また、日本の進むべき未来への展望についても語って頂きます。 企業からは、中国の車載電池世界最大手CATL(寧徳時代)のリージョナル・プレジデントを経て、現在世界第3位の車部品製造企業の日本法人代表を務める多田直純氏より、モビリティ市場での中国、欧州の動向とZF社の市場戦略についてご説明を頂きます。また、長年、低燃費・ハイパワーエンジンの設計、開発で自動車産業をリードし、現在モビリティの電動化を陣頭指揮している岩田和之氏より、移動と暮らしがシームレスに繋がる世界を目指す独自のコンセプト「Honda eMaaS」と、トヨタとの実証実験“Moving e”の取組みについて説明頂きます。 モビリティ市場における世界の動向を多面的な視野で捉え、ご登壇者と討議しながら、今後のモビリティの可能性と日本の未来について一緒に考えてみませんか。 |
| 配布資料 |
|
| 共催、後援、協力 | 【後援】 国立研究開発法人理化学研究所 公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構 |
当日の様子
第40回会合は、「モビリティ市場への新たな挑戦」というテーマで開催しました。
海外の重要な標準化団体の要職に就き、グローバルな人脈を豊富に持つトップアナリストの深尾氏、モビリティ市場のEV化を主導する外資系企業の要職を歴任されている多田氏、日本を代表する自動車製造業の最先端技術の研究者である岩田氏、それぞれの視点からご意見をお伺いしました。
ご講演いただいた内容は下記の通りです。
モビリティ・ゼロ ~500年に一度の革命がもたらす新たな価値創造の時代~
深尾 三四郎氏
Mobility Open Blockchain Initiative(MOBI) 理事
伊藤忠総研上席主任研究員

モビリティ市場の動向は、自動車業界では100年に一度と言われているが、ペストが蔓延し、宗教戦争が起こった500年前の時代と共通するものがあり、まさに500年に一度とも言える価値創造の一大ムーブメントを引き起こしている。そこでは「モノづくり」から「価値づくり」への発想の大転換が求められ、取り組むべきカーボンフットプリントや再生可能エネルギーの利用は、これまでの縦割りの社会を「横ぐし」で繋ぐ発想が求められている。
EVシフト政策における欧米のポリシーメーカーの最大の目的は、新経済圏の創造と雇用創出にある。EV化を行うには、半導体と車載電池が必要であり、それらの製造には十分な調達力が必須となり、国を挙げた経済安全保障としての政策を推し進めなければならない。
脱炭素・サステナビリティは、ほとんどの国が大義として掲げているが、これは世界共通価値の国際通貨であり、政策立案者によるある種の錬金術ということを理解することが重要である。また、サプライチェーンにおける二酸化炭素削減努力や倫理的調達情報を中心としたトレーサビリティを信頼性の高いものとして管理するためには、ブロックチェーンを基盤とする技術が必要であり、MOBIでは規格化、標準化を進めている。
新しい社会の形となる次世代型インターネット社会の「Web3.0」や「メタバース」の到来する社会的な変化をベースとして、自動車業界に何が起きているのかを考える必要がある。
今や自動車・環境規制の重心は、公害対策から経済安全保障の強化へシフトしており、都市鉱山とも言える車載電池における希少資源の囲い込みは、グローバルレベルの資源獲得競争となっている。企業は、調達力を上げるために多くのアライアンスを組んでおり、希少資源活用の効率を上げるための、「リユース」、「リサイクル」を促進させる規制の導入が加速してきた。それらが国益として適うものかを充分に議論し、この流れに上手く乗れるかが、日本政府の動きの重要なポイントとなっている。
日本の食べ物の美味しさは他国に比べ優れており、日本の強みと言える。日本列島のどこに行っても美味いものが溢れており、農産品は差別化の重要なコンテンツとなり得る。農作物の栽培においては、地域ごとに気候、土壌、環境等が大きく異なるので、日本全体として捉えるのではなく、個々の自治体単位で新しい農業を模索していくことがひとつの方法であるのではないか。自動走行で少人化と収益改善を図り、レギュレーションに捉われない私有地での導入を実現し、地産地消で価格転嫁が可能な地域ごとの高品質な農業を推進する。日本各地で新しい農業の試みが行われており、農業は日本のモビリティを活かせる一つの領域ではないかと考えている。
モビリティ市場の最前線から ~中国、欧州の動向とZF社の戦略~
多田 直純氏
ゼット・エフ・ジャパン株式会社 代表取締役社長
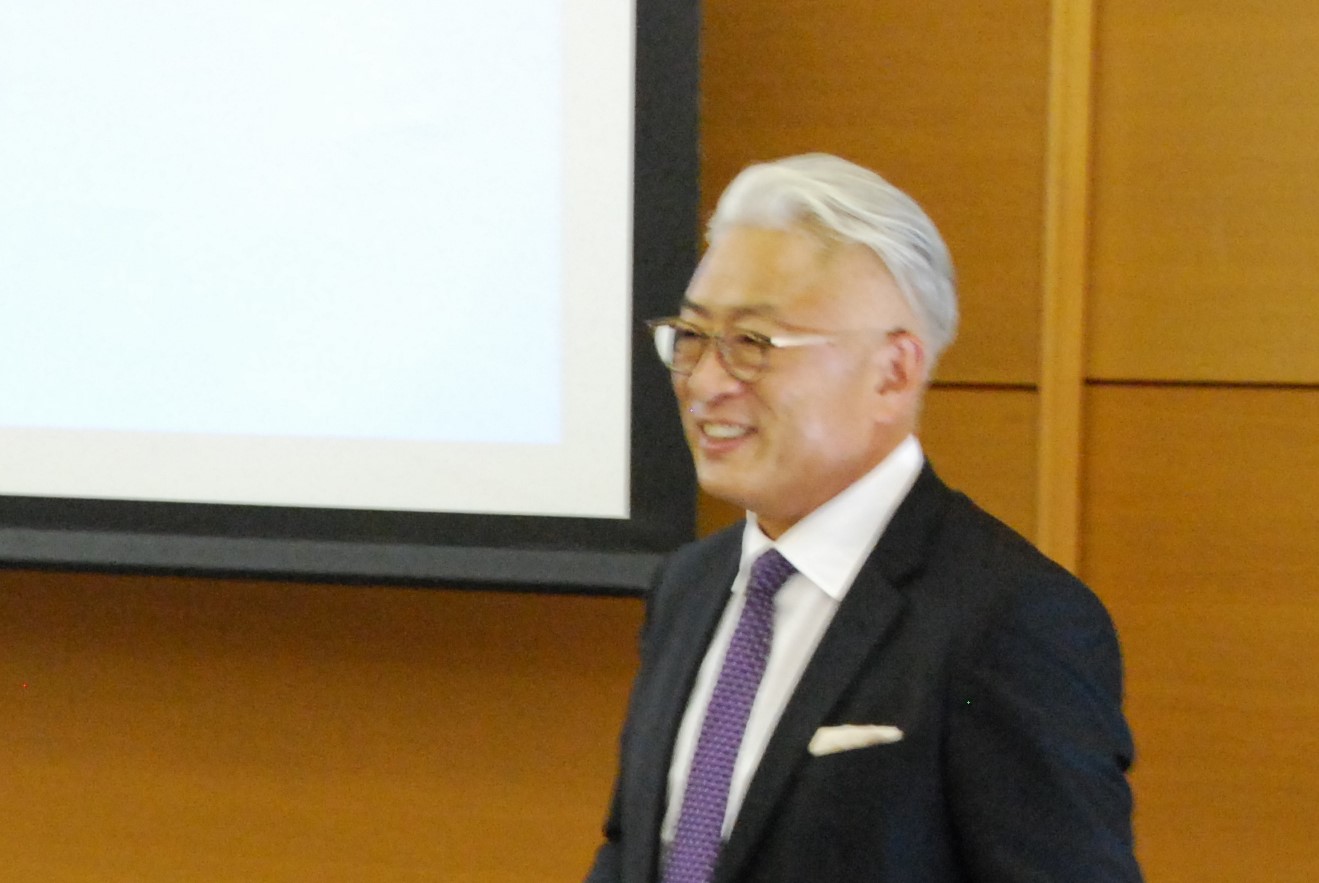
弊社はドイツ南方に本社を持ち、ツェッペリン飛行船のエンジンを回すギアの製造技術をもとに、内燃機関向けのトランスミッションを開発し、現在世界第3位の自動車部品のグローバルサプライヤーである。
昨今、天災や環境破壊に加え、コロナ禍の影響やウクライナ問題、貿易面ではデカップリングなど、産業も世界的に大きな転換期が迎えている。車産業では、特に環境問題に端を発したCO2排出規制の目標値が年々下がっており、その一方で、電動化に必要な電子機器が不足する事態に陥っている。
欧州の動きを見ても、今後は内燃機関を利用する車の使用が禁止され、東京都がディーゼル車の都内走行禁止を行ったように、日本の得意とするHEV、PHEVも市場から締め出されることになるだろう。
パリ協定のCAFE(Corporate Average Fuel Economy)規制も年々厳しさを増し、2020年は95g/kmであったが、10年後には59g/kmをクリアすることが必要となる。弊社のOEM先を見ても、2030年にはほぼエンジン車の生産を終え、BEVのみになる計画である。
車載電池の今後の需要動向は、フォルクスワーゲン1社だけで2030年には517GWhが必要となり、現在世界最大の車載電池生産を誇るCATL社(中国)の5倍の生産量が必要と予測されている。このように需要の伸びが大きく見込まれることから、世界的なバッテリー供給の素材の奪い合いが始まっている。
特に内燃機関製造で他国に勝てない中国は、国を挙げてモビリティ市場のEV化を進めており、企業/機関へのインセンティブの強力な付与や教育・人材育成に集中投資をしている。また、EV化は比較的参入が容易であるため、多数の新興企業が参入し、これまでの品質重視から付加価値重視の戦略で成長の伸びは加速している。日本の企業は最近になって漸くバッテリー企業との関係強化を図り始めている。
車の電動化は、既存のシステムを大幅に塗り替えることで、例えばステアバイワイヤー(steer-by-wire)により、左/右ハンドルを簡単に動かせ、自動運転時にはステアリングを畳めるなど、デザインの自由度が広がり、新しいドライビング経験の提供が可能になる。またソフトウェアの日々のアップグレードにより、より快適なドライビングが可能となる。
バイワイヤーテクノロジーが主流となり、アクセルやブレーキ操作などを電気で伝達し、コネクティビティを利用してクラウドとのタイムリーな連携を図れば、新たな切り口でのデータ分析/解析や設計へのフィードバック、限界状態設計法の改善など、モノづくりを画期的に変えることが可能となる。
再生可能エネルギーの観点からは、電気のピーク使用時のバッファーとして蓄電池が利用できる。クラウドにデータを上げれば、2次利用の残存価値推定も可能となり、電池のトレーサビリティを担保できる。リユースを含むサブスクリプションによるビジネスが可能となる。
電動化でしか成しえない数多くの新しい価値を訴求したEVは、日本の様々な市場での需要が見込まれるが、OEM先からの要望は非常に少ない。日本でのネットワークを築き、パートナーとの連携を通して、日本の新たなモビリティ市場の発展に貢献して行きたい。
エネルギーとモビリティの連携 Honda eMaaS ~ホンダモバイルパワーパック~
岩田 和之氏
㈱本田技術研究所 先進パワーユニット・エネルギー研究所 エグゼクティブチーフエンジニア

モビリティ市場において、世界を取り巻く環境は一変し、2050年の「ネットゼロ」に向けて、CO2削減の大胆な取り組みが始まっている。世界最大のエンジン製造業である弊社も昨年、2040年までに四輪のZEV化を掲げ日本では注目を集めたが、海外では当たり前のことであり、日本の車産業の対応の遅れは明白である。車の電動化で燃料が石油から再生可能エネルギーに変わる時代となり、企業は売って終わる従来型ビジネスからの脱却を迫られている。
モビリティの特長は、一般にCASE(Connected Autonomous Service Electric)で語られるが、電動化の本質はエネルギー(Energy)の変革と、そのシェアリング(Share)にあると考える。エネルギーとしての電池の稼働率を上げ、リターンを増やすためのシェアサービスおよびネットとの連携を図るコネクティッドが重要な要素である。特に、欧州電池規制に基づき、ライフサイクル全体のSOH(State-Of-Health)を把握することが義務付けられたため、データの取得が必須となってきた。
弊社は、MaaSとしての移動に関わる製品ラインと環境にやさしい電気の利用とを、エネルギーを介して繋げる、「HONDA eMaaS」のコンセプトを掲げている。ウェルトウホイールを基本として、縦割りの事業本部制を壊し、IT技術を使って再生可能エネルギーで弊社の全製品を繋いでいくことが、弊社の戦略の方向性である。「eMaaS」を社会のエコシステムとして、他社製品にも拡げ、再生可能エネルギーの普及・拡大に貢献したい。
これまでの車づくりでは航続距離を伸ばすことが重要な目的であったが、EVでは、それに加えバッテリーの充電時間や車両への搭載重量のバランスが求められる。バッテリーは電欠が怖くて「0」までは使えないので、無駄なバッテリーを搭載することとなり、航続距離の伸長、車両の重量増し、価格の高騰の悪循環に陥る。
弊社は軽量の着脱式バッテリーを考案した。着脱式バッテリーは、平時には再生可能エネルギーのバッファーとして利用し、有事には分散発電、分散電源として、大災害へのレジリエンスとして大きな効果が期待できる。既に外部給電の実証実験を始めており、弊社のバッテリーは非常に質が高く、医療機器等への使用でも問題なく稼働することが立証できた。
リユース、リサイクルを念頭に置き、ゴミの抑制、CO2削減のみではなく、地球全体のバッテリー生産量を抑制し、走る電源として従来のガソリン車では実現出来なかった価値を顧客に訴求し、市場に展開していくことがもっとも重要であると考えている。
[インタラクティブ・セッション]
登壇者三人に共通するのは、EV市場での海外勢(欧米/中国)の優位は歴然としており、日本企業は「EVにどのように取り組むか?」を議論する時期は過ぎ、「やる?やらない?」の二者択一を迫られている状況にあるということ、また、その中で生き残りを掛けて新たなビジネスモデルに挑戦しているホンダの力強さが非常に強く印象に残りました。
-

講演風景 -

インタラクティブ・セッションの様子







